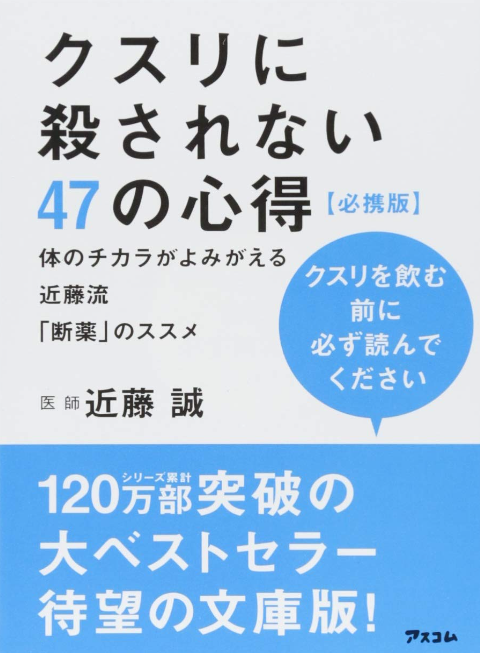【コンビニオーナーぎりぎり日記】

インフォメーション
| 題名 | コンビニオーナーぎりぎり日記 |
| 著者 | 仁科 充乃 |
| 出版社 | 発行 三五館シンシャ / 発売 フォレスト出版 |
| 出版日 | 2023年8月 |
| 価格 | 1,430円(税込) |
「365日24時間、気の休まらない仕事」
現役オーナーが告白する、
コンビニ経営、その光と影
――お客さまは何さまですか?
近隣にコンビニが増え、店舗の乱立で売上げは激減。
お客の取り合いばかりでなく、従業員も奪い合いとなり、今では時給を上げても応募者はゼロ。人手も足りなきゃ、人件費も削らなきゃで、オーナーである私たち夫婦は休んでなどいられない。
――本書に書かれているのはすべて、コンビニオーナーとしての30年間で実際に私が体験したことである。
引用: フォレスト出版
ポイント
- 「コンビニの深夜営業を規制して!」と、私は声を大にして言いたい。夜の1時に閉めて、朝の5時に再開でもいいので、せめて深夜の数時間を安眠できる時間帯にしてほしいのだ。
- コンビニオーナーになった当初、私が苦しんだのは人間不信、というより恐怖だった。今、目の前にいるこの人が、どのタイミングで怒鳴り出すかわからない、そんな恐怖感の中で毎日を過ごしていたのだ。
- いつのまにか私は、心臓に毛が生えたようになり、初めてお客にも平気で話しかけるおばさんになっていた。お客とも仲良くなり、常連さんとは家族のような間柄で、パートさんもバイトの子も本当に大事なファミリーである。
サマリー
コンビニ経営その最前線
年中無休:葬儀に出るときの作法
「コンビニの深夜営業を規制して!」と、私は声を大にして言いたい。
夜の1時に閉めて、朝の5時に再開でもいいので、せめて深夜の数時間を安眠できる時間帯にしてほしいのだ。
この年になり改めて、自分のやっているコンビニという商売は非常識だと感じる。
1年365日、1日24時間、何があっても、とにかく営業し続けなければならない。
しかもそれは、一個人の小さな小売店にすぎないのだ。
親戚に結婚式があれば、半年も前からパートさんやバイト学生に頼み込み、万が一の場合も考えて、予備スタッフを確保しておかなければならない。
あらかじめ予定がわかっている結婚式ならまだいいが、先日、この店を出したときにも力になってくれた、恩義のある叔父が亡くなった。
夫と一緒に葬儀に出席しようとしたが、人手が足りないのだ。
休みのバイト学生やパートさん達に片っ端から電話したが都合がつかず、仕方なく以前勤めてくれていたバイト学生たちに連絡し、やっと確保することができた。
そうまでして出かけた葬儀だったが、骨上げの最中に携帯が鳴った。
「日比野くんが来ないんです」
ようやく探し当てた元バイトの子である。
日比野くんが来ないと、それまで勤務していたパートの三宅さんが退勤できず、困って電話してきたのだ。
「子どものお迎えがある」とすがるような声でせっつかれ、葬儀の席を外し、夫と2人で手分けして、今すぐ入れる助っ人を探し始めた。
15分程して1人見つかり、ほっと一息ついた瞬間、またポケットの携帯が鳴った。
「すみません。今、日比野くんが店に来ましたので、もう大丈夫です!」
結局、日比野くんは25分遅れでやってきたのだ。
今、大急ぎで店に向かってくれている子にも、時給を払わないといけない。
静かな火葬場の隅で、私と夫は顔を見合わせたのだった。
コンビニオーナー、始めました
心が汚れていく:人間不信と罪悪感
コンビニオーナーになった当初、私が苦しんだのは人間不信だった。
不信というより恐怖といった方がいいかもしれない。
「早くしろ!」「どうしてくれるんだ!」しょっちゅうお客に怒鳴られた。
今、目の前にいるこの人が、どのタイミングで怒鳴り出すかわからない、そんな恐怖感の中で毎日を過ごしていたのだ。
一方で、私の中には変な自尊心と優越感が存在していた。
それまで私は幼稚園教諭として勤め、結婚後は臨時で保母していたので、幼い子どもの可愛い笑顔と接する仕事から、見知らぬじいさんに怒鳴られる仕事に急変したのだ。
私は心が確実に汚れていくのを感じた。
怒鳴り続けるお客に頭を下げながら、心の中では「育ちの悪い奴が…」などと悪態をつく。
自分が差別や偏見を持っていることもよくわかった。
私はなんて嫌な人間なんだろうと毎日思い知らされ、そんな事実を私に突きつけたこの仕事も嫌いだった。
もう一つ苦しかったこと、それは食品の廃棄だ。
商品の廃棄時間が来ると「ピンポンパンポン〜♪」と軽快な音楽が店内に流れる。
時間がきた商品をカゴに取り、レジで廃棄入力をして、カゴごとウォークインクローゼットに入れる。
ここに保管しておいた廃棄食品は、後でまとめてゴミ袋に入れ込み、店内で出たゴミや、お客様が捨てたゴミと一緒になるのだ。
「まだ食べられる商品」が「ゴミ」に様変わりする瞬間である。
この時の気持ち、まだ十分に食べられるものを捨てる罪悪感を、どう表現すればいいのだろうか。
コンビニを始めてすぐ感じたこの違和感は、30年経った今も変わることはない。
お客様は何さまですか?
仲良しのつもりが
毎日、午後1時過ぎに来店し、レジで会話をしていくおばあさんがいた。
顔をクシャクシャにして笑い、実に楽しそうなので、私もパートさんも仲良しのつもりだった。
ある日、買い物の際、レジでおばあさんが1万円札を出した。
私は8,000円のお札をお釣りとして渡し、そのあと小銭を返すつもりだったが、いつものようにおばあさんに話しかけられたので、先に8,000円渡したことを忘れ、小銭とともに再び8,000円をおばあさんに渡してしまったのだ。
その数時間後、レジに8,000円が不足していることに気づき、慌ててビデオチェックした。
ビデオには、私が2度目に8,000円を渡した瞬間、「え!」という顔をしたあと、そそくさと札を財布にしまい、店を後にしたおばあさんが映っていたのだ。