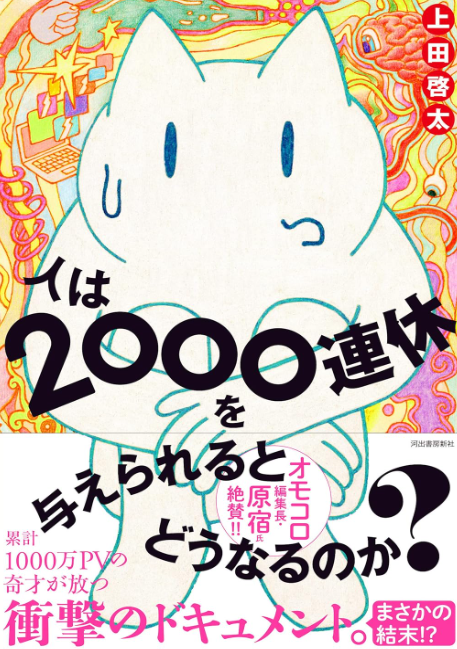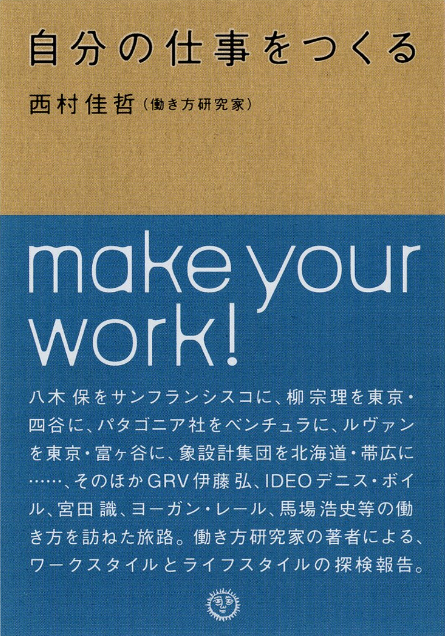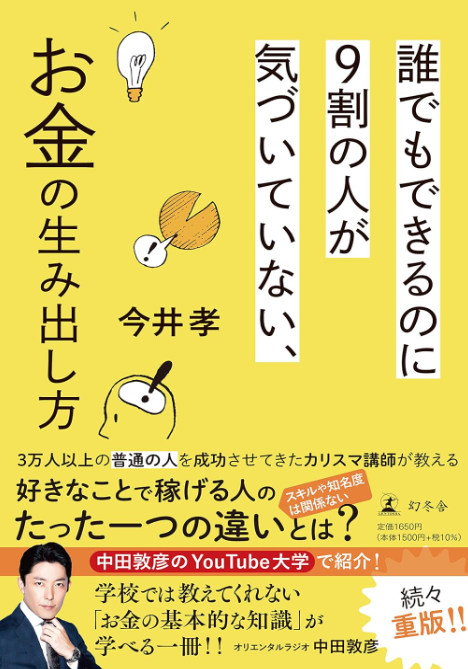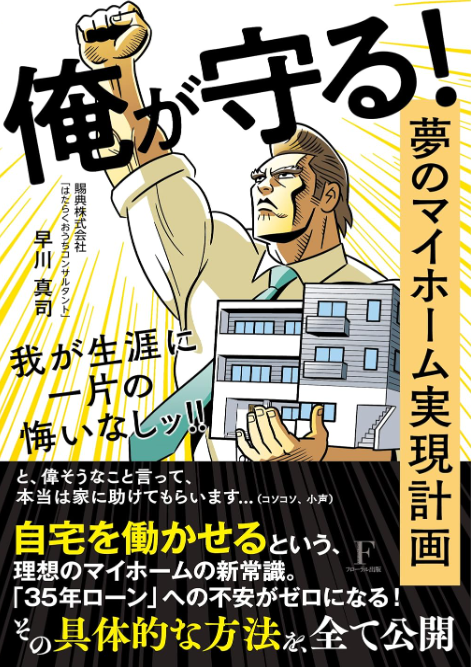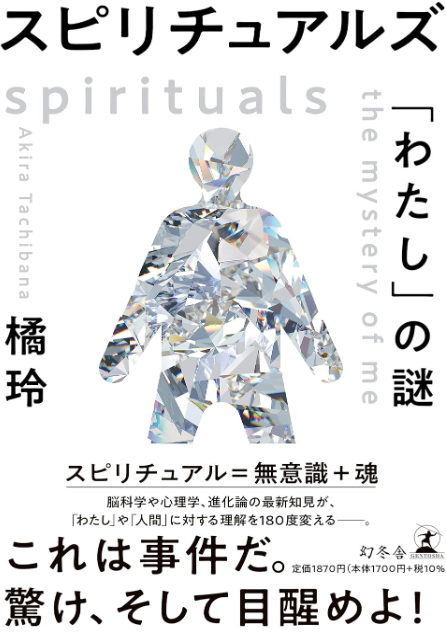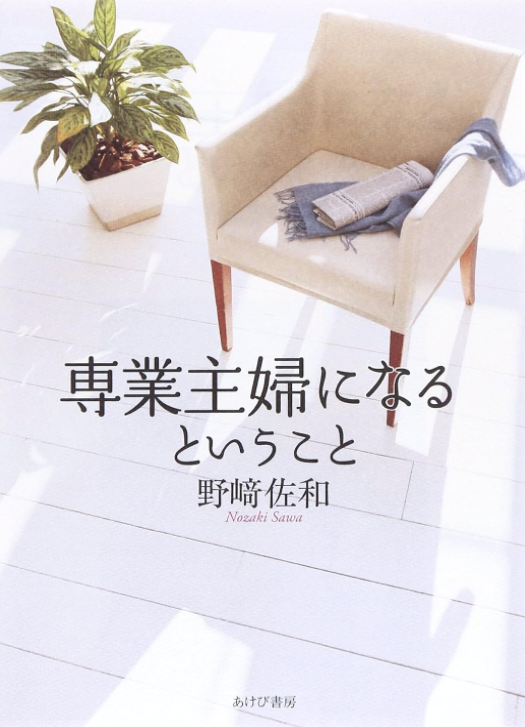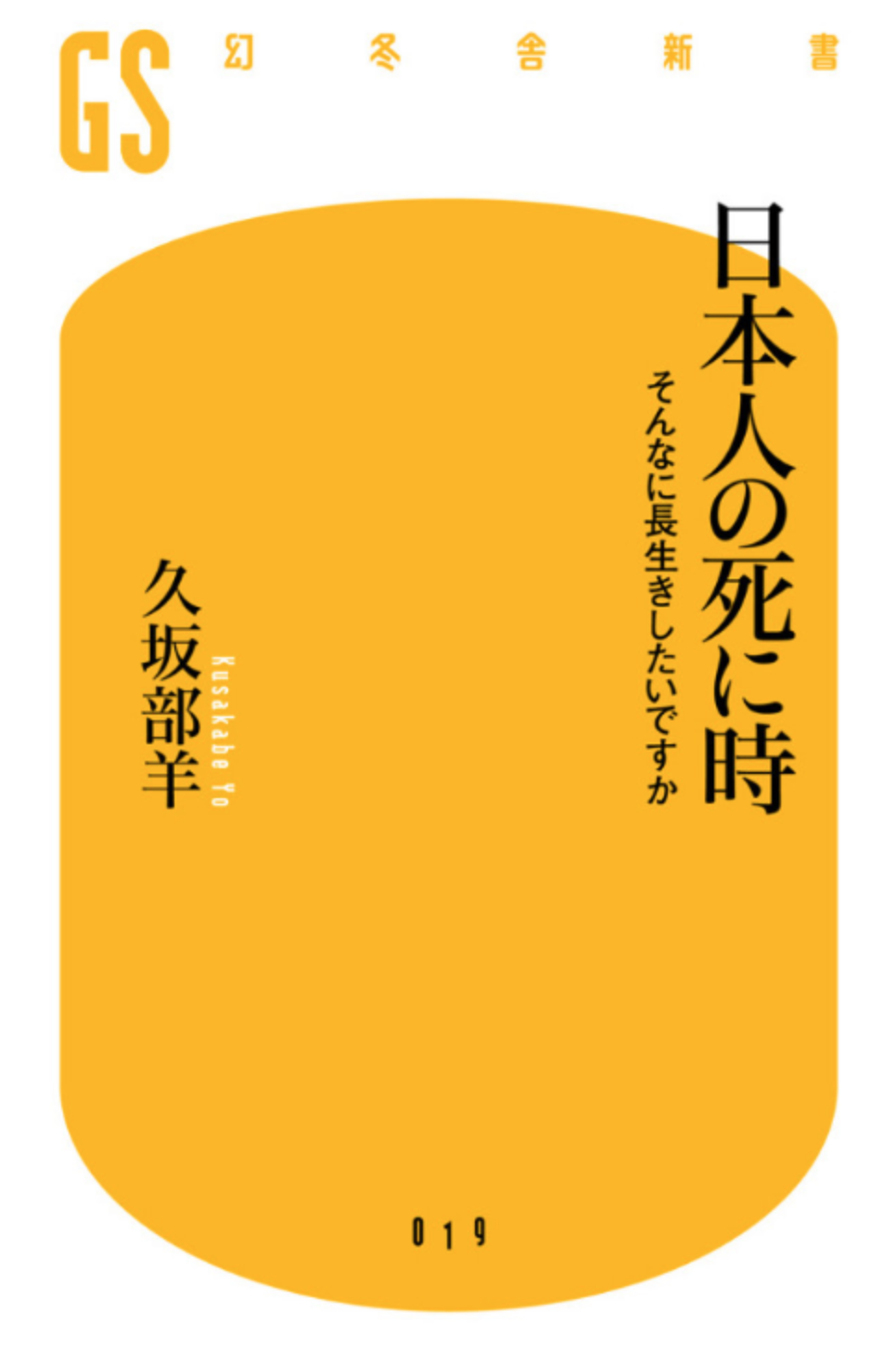【ドキュメント・銀行の預貯金過誤払い責任を問う】

インフォメーション
| 題名 | ドキュメント・銀行の預貯金過誤払い責任を問う |
| 著者 | 矢吹紀人 |
| 出版社 | あけび書房 |
| 出版日 | 2009年7月 |
| 価格 | 1,760円(税込) |
―預けたお金を返してください!
盗難や偽造された通帳やカードで、自分の口座からいともたやすく預貯金を引き出された被害者たち。
銀行に訴えても、銀行は何の責任も負おうとしない。
警察に訴えても、真剣に対応してくれない…。
先進諸国では銀行の非が認められているにもかかわらず、日本では被害者は泣き寝入りを余儀なくされてきた。
判例も銀行に有利なものばかりであった。
しかし、彼らは起ちあがった。
そして、集団訴訟の末、銀行に勝った。預金者保護法も制定させた…。
たちまち増刷の話題の書!
柳田邦男氏絶賛・推薦の渾身のドキュメント。
引用:あけび書房
ポイント
- 預貯金過誤払いが「社会的」な問題であり、被害の実態を世の中全体に強くアピールし、社会的な問題にしていくことでしか、銀行側の対応を改める事はできない
- 銀行側は、従来どおりの「印影確認だけで十分足りる」という主張をあいもかわらず繰り返してくる
- 預貯金過誤払いの被害は、ときに被害者本人だけでなく、家族や周囲の人びとの人生を変えてしまう
サマリー
はじめに
思いもしない通帳盗難で預金を引き落とされ、銀行や警察の態度に泣かされてきた。
弁護士に相談しても、電話口で「あきらめなさい」と何度いわれたことか。
しかし、今回相談した弁護士は明らかに、他の弁護士とは反応が違っていた。
とにかく「話を聞いてもらえる」ことに、希望を感じることができるのだった。
鳴り止まぬ被害の電話
被害者になった弁護士
マンションや事務所のドアカギをこじ開けて侵入する「ピッキング犯」の一つの犯行手口は、通帳などを盗んだ後にカギを壊すなどして、ドアを開かなくしておくことだった。
居住者がなんとかカギを開けようと手間をとられている間に、金融機関で預金をおろす時間をかせぐことが目的だ。
不審に感じてすぐに室内を確かめたが、机の引き出しにしまってあった2冊の銀行預金通帳と、印鑑が盗まれていることがわかった。
それぞれの金融機関に引き出しを止めるよう連絡をいれたが、すでにこのとき、二つの通帳とも、預金の大半が引き出された後だったと、銀行に連絡してわかった。
被害額は通帳2冊分で、合計1,400万円に達していた。
被害者しか世の中を変えられない
自身も被害にあった野間弁護士のもとには、10件以上の預貯金過誤払いの被害者から相談が集まってきた。
その中には高額な被害にあった人も少なくなかったし、本人確認などをきちんとしなかった銀行の落ち度が明らかだと思えるケースも何例もあった。
預貯金過誤払いが「社会的」な問題であることをしだいに強く感じるようになっていった。
だとすれば、被害の実態を世の中全体に強くアピールし、社会的な問題にしていくことでしか、銀行側の対応を改める事はできないだろう。
そのためには、たとえ勝算が少なくとも、被害者が法的な手段に訴える必要がある。
事件は自分一人の問題ではない。
預貯金の被害者が救済されず、銀行が涼しい顔をしていられるいまの社会のありかたを変えるには、社会的な問題として訴えていくしかない。
多くの被害者が抱いてきた考えと、弁護士たちの考えが一致した。
これが銀行の本質か
涙を超えた被害者シンポジウム
「私は自宅から銀行の預金通帳と印鑑を盗まれました。4つの支店から2日間にわたって、合計で約1400万円を引き出されました。」
2003年6月7日、預貯金過誤払被害対策弁護団が主催者となってシンポジウムを開いた。
前年の12月9日に第一次の集団訴訟をおこなった。
70人にのぼる被害者がいっせいに提訴するという、預貯金過誤払い事件では過去にない例だったが、新聞などマスコミの取り上げ方は、弁護団が期待したほど大々的なものではなかった。
「被害者がこれほど多い社会問題だ」という点が上手く伝わらなかったこともあっただろう。
そこで弁護団では、マスコミ関係者に集団訴訟の意味を正確に「レクチャー」して、さらに大きく取り上げてもらう取り組みを始めた。
「例年、ゴールデンウィークは、マスコミもネタが不足するときなんだ。この時期に取り上げてもらうよう働きかけて、1か月後ぐらいにシンポジウムをやる。こういう手で行きましょう。」