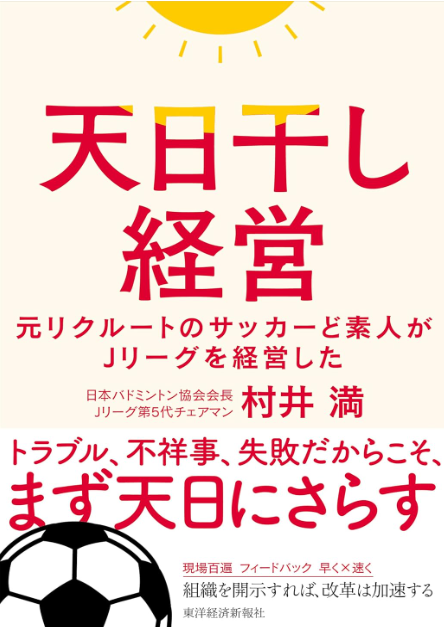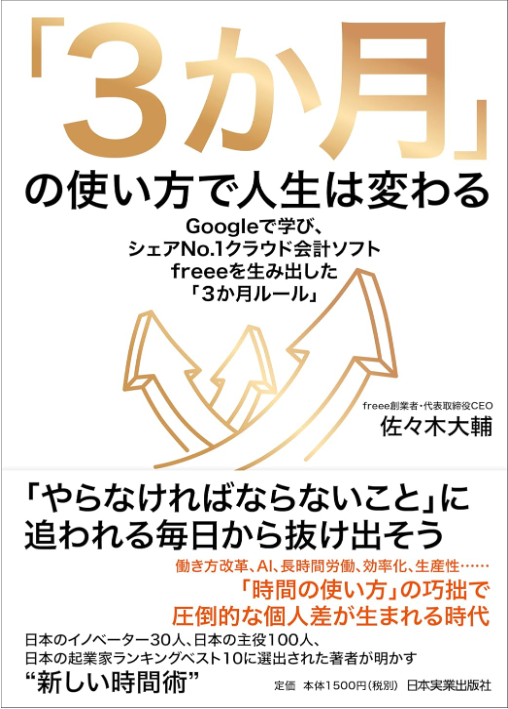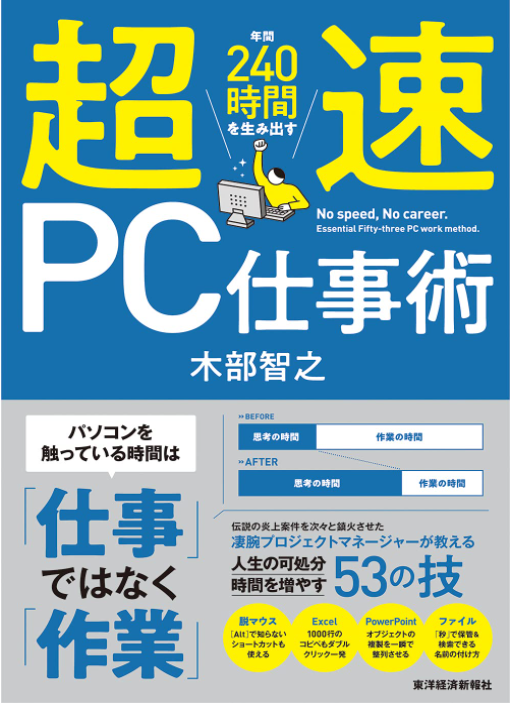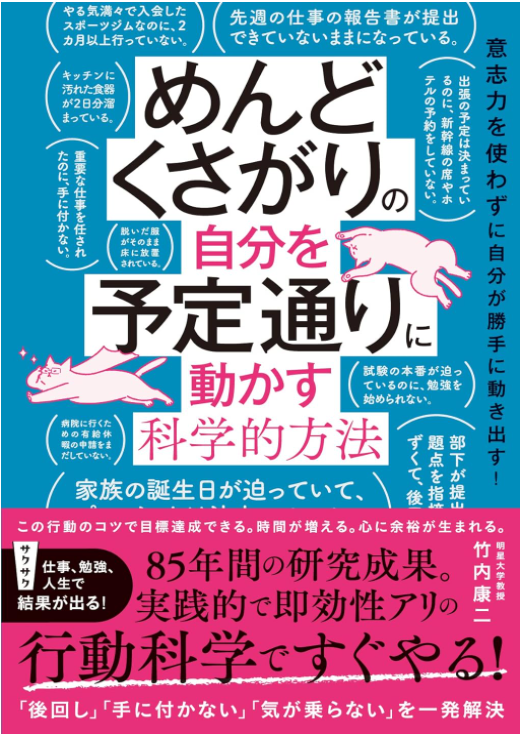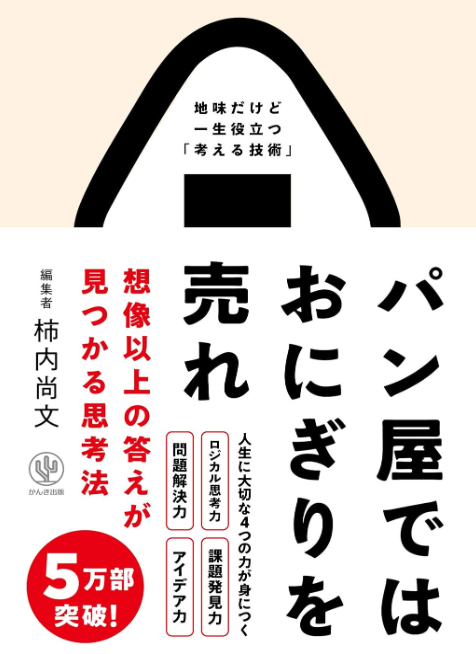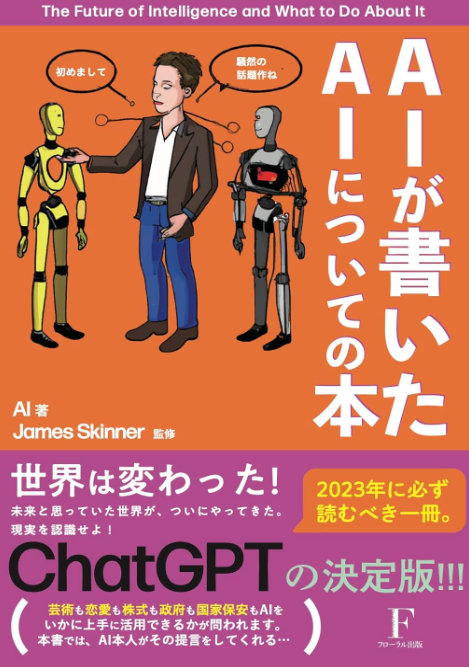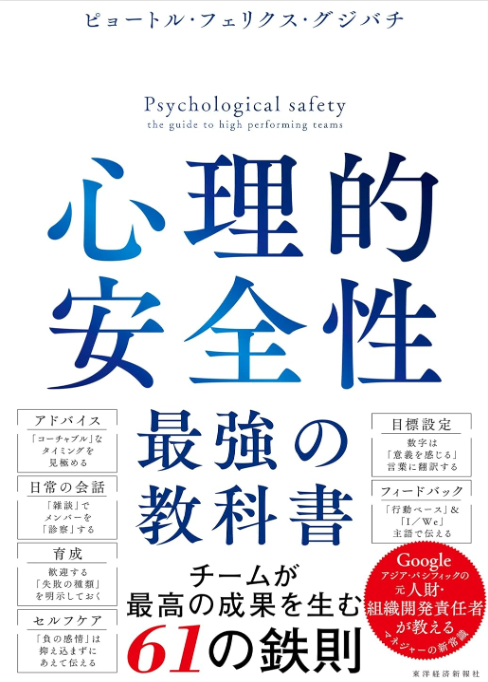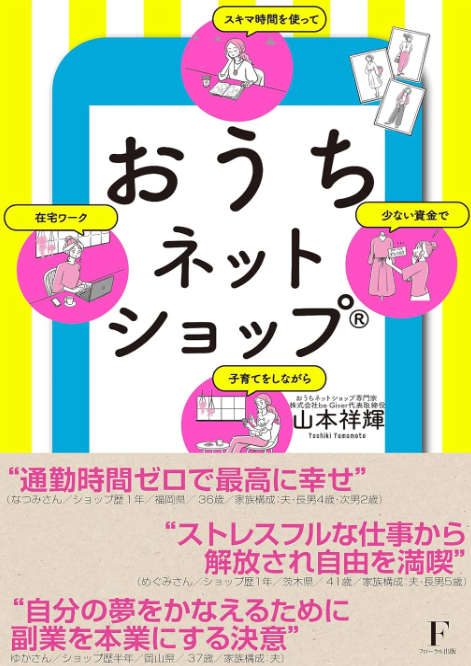【ビジネスモデルの教科書:経営戦略を見る目と考える力を養う】
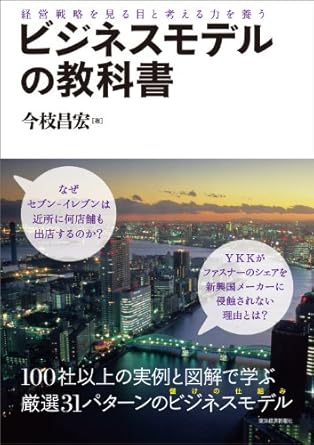
インフォメーション
| 題名 | ビジネスモデルの教科書:経営戦略を見る目と考える力を養う |
| 著者 | 今枝 昌宏 |
| 出版社 | 東洋経済新報社 |
| 出版日 | 2014年3月28日 発売 |
| 価格 | 1,980円(税込) |
実際の企業名&ケースをもとにビジネスモデルを解説。戦略的センスと経営戦略策定力を鍛える実践的ガイドブック。
引用:東洋経済新報社
ポイント
- 強い戦略があればビジネスで成功するわけではない。その戦略を支える仕組みも含めて事業体として強いビジネスが成功する!
- 戦略立案の過程を勉強するだけでは、なかなか有効な戦略を生み出すことができない。
- 有効な戦略を型として整理した「ビジネスモデル」を学ぶのが効率的!
サマリー
はじめに
本書の目的は、読者に経営戦略を策定する能力やセンスを高めていただくことにある。
具体的には、自社にとって効果的かつ持続可能であり、実現可能な戦略を、よりスピーディに策定する能力を養っていただきたいのである。
また、競合会社の動向から、彼らが「何を狙っているのか?」「なぜ強いのか?」を即座に理解し、それに対応する力を身につけていただきたい。
そのために本書では戦略、つまり「誰に」「何を」売るのかという顧客と提供価値の選択だけでなく、戦略を支える経営資源や使い方などの仕組みを包括した「ビジネスモデル」に注目している。
強い戦略があればビジネスで成功するわけではない。その戦略を支える仕組みも含めて事業体として強いビジネスが成功するのである。
ビジネスモデルと戦略の関係
戦略だけではうまくいかない
本書の目的は戦略策定の力、戦力を読み解く力を養うことである。
そのために、誰に何を売るかという市場でのポジショニングとしての戦略だけに目を向けるのではなく、戦略を支える業務活動や経営資源などの内部の仕組みを組み合わせたもの=ビジネスモデルに目を向ける。
なぜそうするのかと言うと、従来の戦略論ではポジショニングが重視され、戦略が主であるとすると、社内の仕組み等は従として扱われてきた。
その結果、戦略の策定において実現可能性が検討されなかったり、戦略を実現する際に内部の仕組みを軽視してしまったり、結果として実現が頓挫するということが頻繁に起こった。
一見すると戦略として間違っていなくても、競合による戦略の模倣可能性についても正しく理解しないため、結果的に戦略自体が質の低いものになることもある。
これらの失敗は、戦略を考えるうえで、それを支える社内の仕組みや経営資源の検討や理解が不十分であったからに他ならない。
競争優位の源泉は戦略よりもビジネスモデル
なぜ戦略を考える際に、それを支える社内の仕組みや経営資源について検討されないのか。
それは多くの場合、戦略の立案者と戦略の実行者とが異なる担当者であることに起因している。
また、それぞれを別々のコンサルタントが支援するといったことが、戦略とそれを実現する仕組みの分断に更なる拍車をかけていることがある。
持続可能な競争優位の源泉は、従来戦略として語られてきた顧客と提供価値の選択、すなわちポジショニングよりも、むしろ業務活動や経営資源など資源を支える仕組みの方にあることが多くある。
さらに、戦略とそれを支える仕組みの間には連関が存在したり、循環が生じて自己再強化されたりするようになっていることもある。
つまり、成功しているビジネスは、戦略として強いのではなく、その戦略を支える仕組みも含めて事業体として強い、比喩的に言えば「生き物」として強いということが言える。