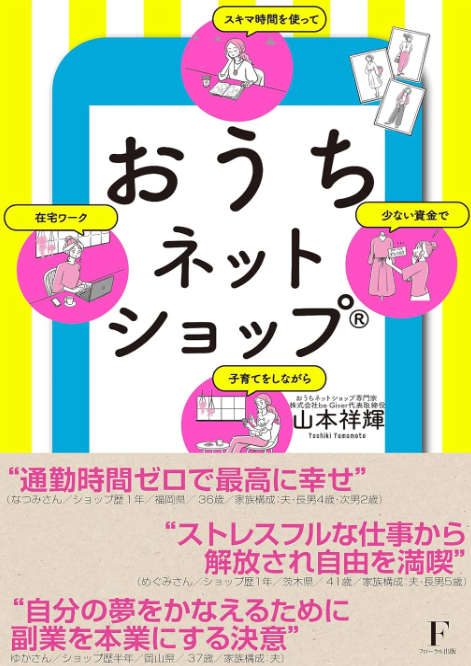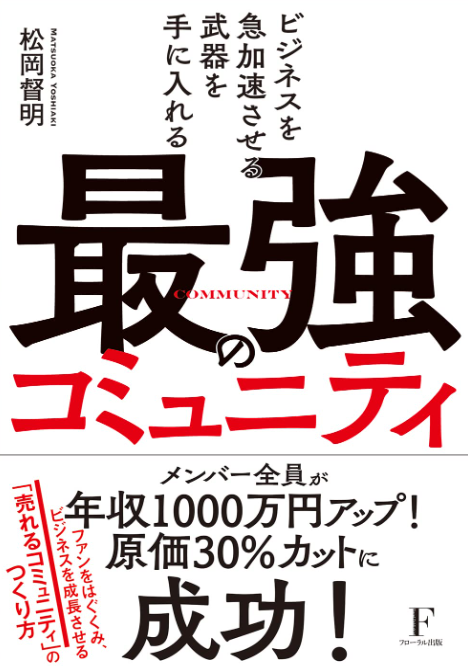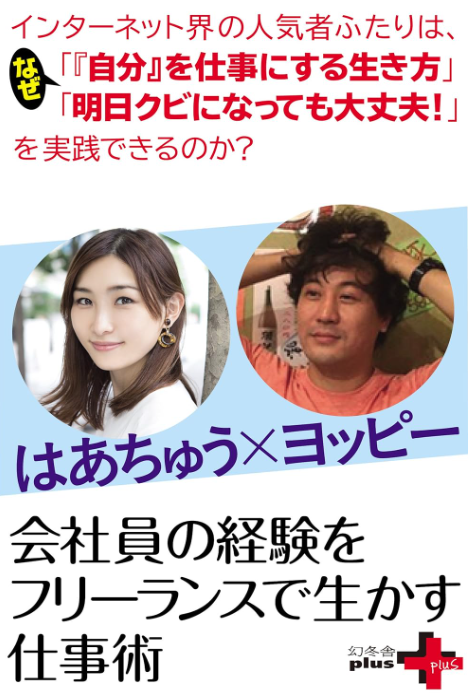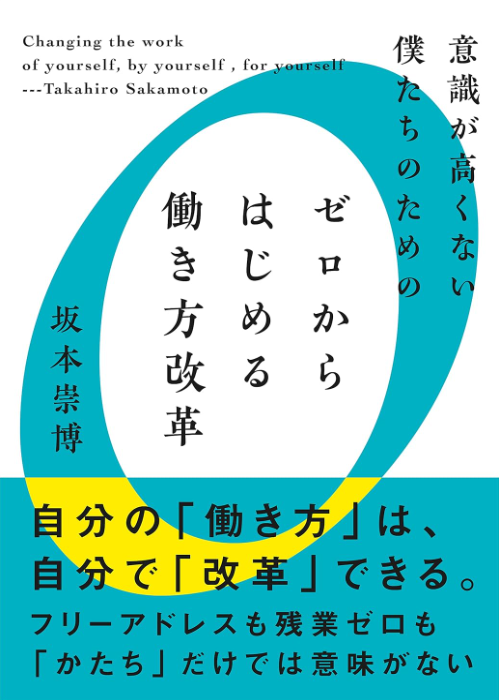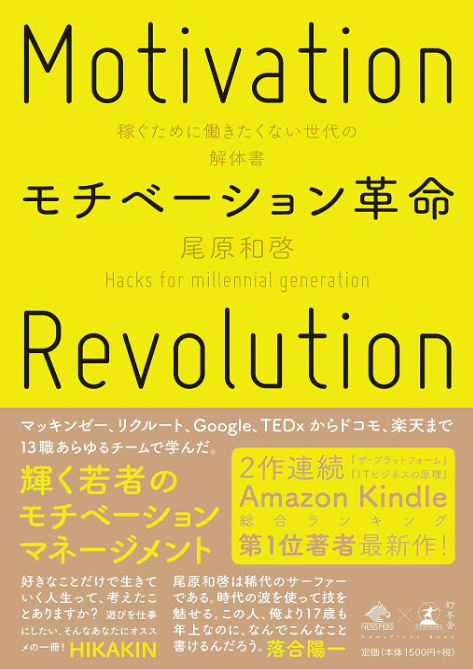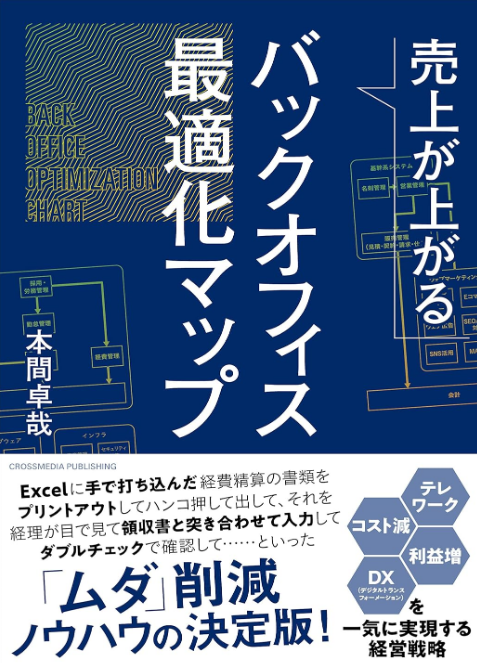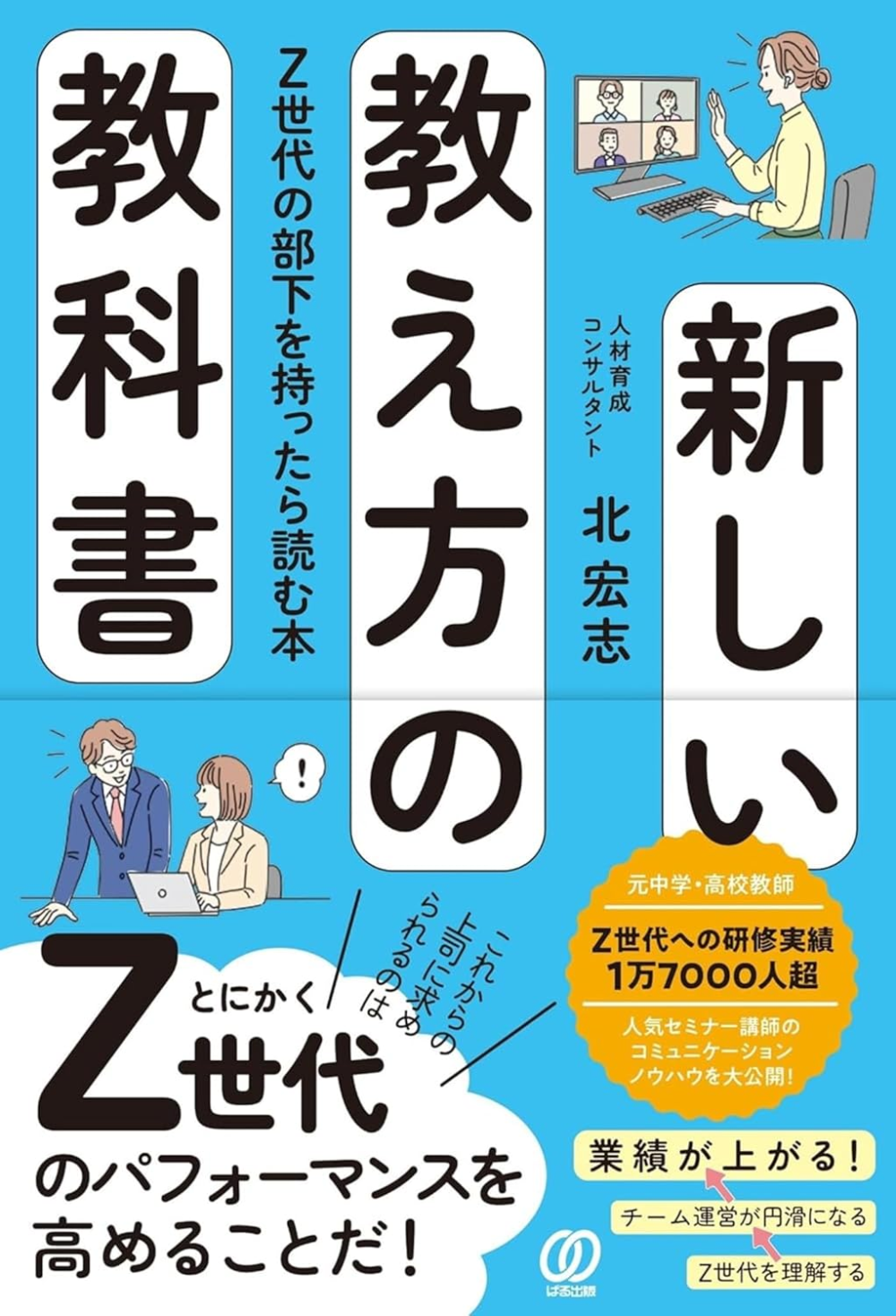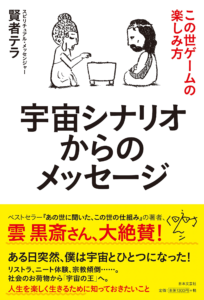【地方創生大全】
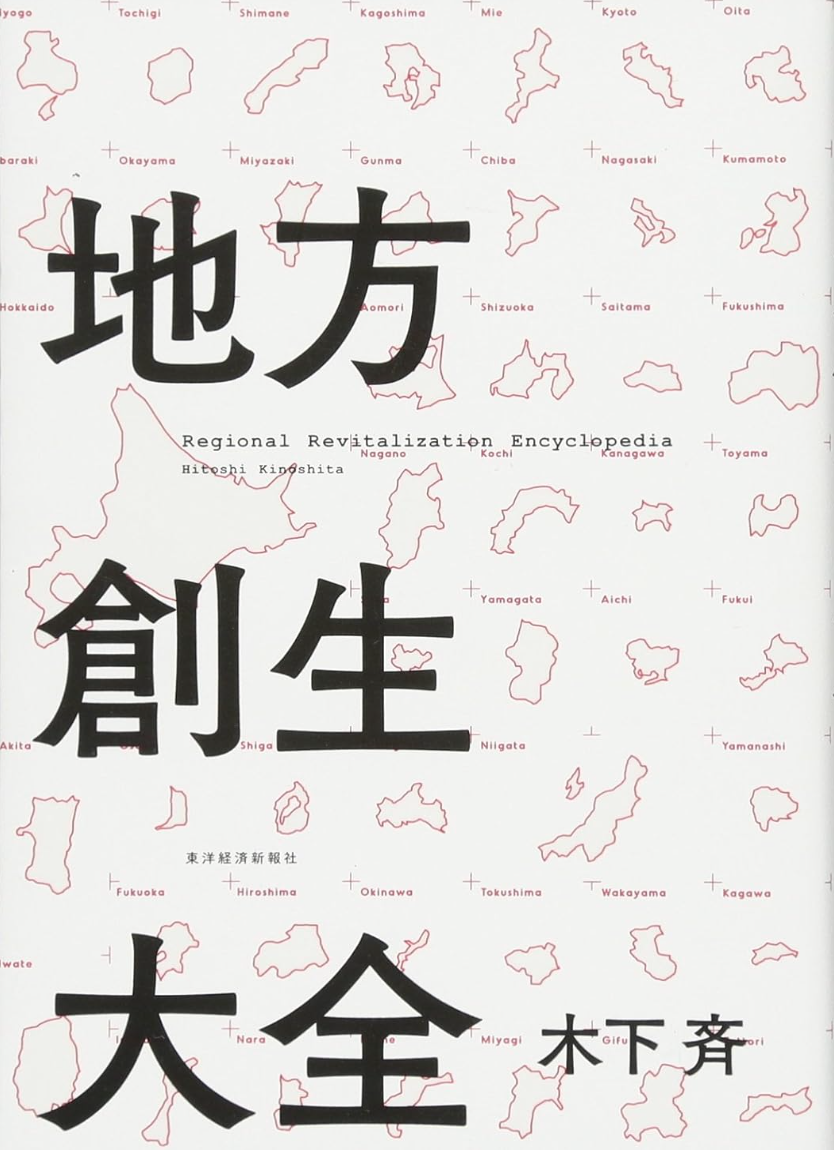
インフォメーション
| 題名 | 地方創生大全 |
| 著者 | 木下 斉 |
| 出版社 | 東洋経済新報社 |
| 出版日 | 2016年10月7日 |
| 価格 | 1,650円(税込) |
地方再生請負人、地方創生のカリスマと称される著者が、多くの成功事例・失敗事例をもとに解説する「地方創生&街づくりのルール」。
引用:東洋経済新報社
ポイント
- 人生で初めてかかわった地域活性化事業で貴重な取り組みを経験した。
- 過去に問題があった進め方に新たな名前を付けて、再度実行してしまうというのが地方創生政策における大きな問題なのである。
- 「都市部が期待する“心温まるきれいな地方の成功ストーリー”」ばかり取り上げられている。
サマリー
はじめに
2014年の「地方消滅論」に端を発した地方創生政策が立ち上がり、地方創生総合戦略なるものが策定され、2015年から全国各地で展開されている。
地方に携わる仕事を18年間している私としては、地方に光が当たるのは嬉しい。
しかし、地方創生を目指すそのアプローチについては、大いに心配を抱かせられる。
2016年6月にNHKが、内閣府が先進的と紹介する75の事業すべてについて調査をした結果、目標を達成したのは全体の4割に当たる28事業であった。
初年度とはいえ、自治体が自ら企画して国から予算をとり、かつ国側も先進的であると全国に紹介した事業でさえもこの状況にある。
たしかに地方政策は、1~2年で地域全体が再生するような事業ではない。
しかし、自ら立てた毎年の目標さえも達成できないようでは、将来にわたって成果を出すことは期待できない。
なぜこのような問題となるのか。
複数の視点から整理していく。
地方政策の難しさ
地方創生は「事業」であるべき
私は高校1年生のときに、早稲田商店会の地域活性化事業に関わった。
年間予算が100万円もない貧乏商店会で、そもそも法人でさえもなく、事務局員もいなかった。
しかし、そこで取り組んでいた「環境まちづくり」は大きな注目を集めた。そのポイントは次の3点である。
・経済団体が環境をテーマに地域活性化活動に取り組んだ
・補助金は活用せず、自ら稼ぐ地域活性化事業だった
・「民間主導・行政参加」という、従来とは逆の構造で取り組んでいた
人生で初めてかかわった地域活性化事業でこのような貴重な取り組みを経験した。
その後、事業の失敗も含めさまざまな経験を経て「事業としての地方創生」を強く意識するようになったのである。
地方政策の失敗は繰り返される
地方創生の先行型予算で取り組まれた代表的な政策のひとつは「プレミアム商品券」である。
日本全国の99.8%の自治体がプレミアム商品券を発行し、1589億円の予算が請求され、執行された。
しかし、そもそも地域振興券などの政策効果は4分の1、あるいは3分の1程度と言われており、地方活性化策としては「効果のないばらまき」とされている。
過去に問題があった進め方に新たな名前を付けて、再度実行してしまうというのが地方創生政策における大きな問題なのである。
これらは自治体や行政の問題だけでなく、民間側もこのような策に乗っかって商売している節もある。
さらに、この政策決定について予算をつけている国会、地方議会という存在もあり、彼らを選んでいるのは、国民一人ひとりなのである。
このような構造的な負の連鎖を断ち切るためには、過去の失敗を見て見ぬふりをするのではなく、私たちみんなが過去の失敗と向き合わなくてはならないのである。